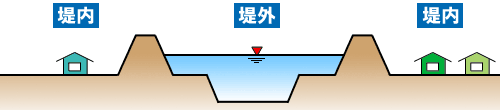河川改修事業 救急内水対策事業
ページ内目次
河川改修事業 - 天塩川水系
救急内水対策事業
事業の目的
内水氾濫がよく起こる、内渕川、旭東川、美深6線川、9線川、島見川の地区では、状況に応じてポンプを使って内水排除を行ない、被害の軽減をはかっています。
事業の概要
(1)対象
内水被害が頻発しており、比較的小規模なポンプで被害の軽減が可能な地域にて行っています。
(2)実施
吸水槽とポンプ等の整備を行っています。
救急内水概要表
| 地 区 名 | 対 象 河 川 名 | 流域面積 (平方キロメートル) |
最大排水能力 (立方メートル/s) |
ポンプ台数 (台) |
備 考 |
| 内渕 | 内渕川 (普通河川→準用河川) |
10.77 | 5 | 5 | |
| 旭東 | 旭東川 (普通河川→準用河川) |
1.62 | 3 | 3 | |
| 美深6線 | 美深6線川 (1級河川) |
1.50 | 3 | 3 | |
| 美深9線 | 9線川 (普通河川→準用河川) |
1.48 | 2 | 2 | 音威子府へ1台 |
| 音威子府 | 島見川 (普通河川→準用河川) |
4.28 | 3 | 2 | 美深9線より1台 |
| 合計 | 19.65 | 16 | 15 |
-
 美深6線
美深6線
-
 内渕
内渕
内水氾濫とは
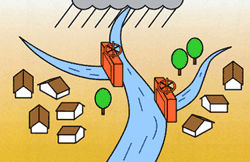
雨が降ると河川の水位が上昇します
雨が降ってくると河川の降水量が増し、それにともない大きな川と市街部を流れる川の水位も上昇してきます。長期的な雨や集中豪雨の場合、洪水氾濫の恐れが出てきます。
雨が降ってくると河川の降水量が増し、それにともない大きな川と市街部を流れる川の水位も上昇してきます。長期的な雨や集中豪雨の場合、洪水氾濫の恐れが出てきます。
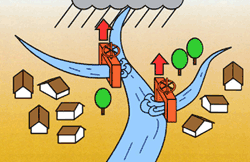
樋門を開き、大きな川へ放水
市街部を流れる川の水位が上昇してくると、周辺の住民や家屋への被害が生じないようにするため樋門を開き大きな川へ放水します。
市街部を流れる川の水位が上昇してくると、周辺の住民や家屋への被害が生じないようにするため樋門を開き大きな川へ放水します。
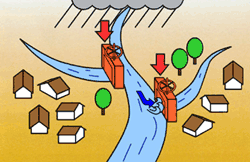
樋門を閉じて、逆流を防止
水量が増加するとともに大きな川の水位も上昇してきます。市街部を流れる川へ逆流する恐れが出てきますので樋門を閉じて逆流を防止します。
水量が増加するとともに大きな川の水位も上昇してきます。市街部を流れる川へ逆流する恐れが出てきますので樋門を閉じて逆流を防止します。
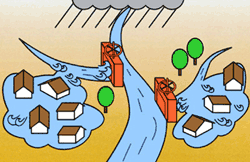
内水氾濫が起きてしまう
樋門を閉じたため、市街部を流れる川から水があふれてしまい内水氾濫が起きてしまいます。
樋門を閉じたため、市街部を流れる川から水があふれてしまい内水氾濫が起きてしまいます。
内水(ないすい)・外水(がいすい)について
河川には、水害から人を守るための堤防という人工構造物があります。その堤防で守られているところ、つまり、家屋などが立っている側を「堤内」、そして川側を「堤外」といいます。
そして、「堤内」の河川の水を『内水』、河川側の「堤外」の水を『外水』と言います。
そして、「堤内」の河川の水を『内水』、河川側の「堤外」の水を『外水』と言います。
また、河川の氾濫の際、堤内の土地が浸水した場合、その水を取り除くことを「内水排除」といいます。
そして、本川から洪水があふれることを「外水氾濫」と言います。本川から洪水があふれたのではなく、街や農地に雨が降り、堤外へ流れ出す事ができずにあふれてくることを「内水氾濫」といいます。
なぜ、私たちの生活している場所(川の外)を「内」、堤防の向こう側(川の中)を「外」というのでしょうか。それは、洪水の際には、人々は堤防によって流れてくる水から守られており、その人々がいる場所が内側になる、という考えからと言われています。
そして、本川から洪水があふれることを「外水氾濫」と言います。本川から洪水があふれたのではなく、街や農地に雨が降り、堤外へ流れ出す事ができずにあふれてくることを「内水氾濫」といいます。
なぜ、私たちの生活している場所(川の外)を「内」、堤防の向こう側(川の中)を「外」というのでしょうか。それは、洪水の際には、人々は堤防によって流れてくる水から守られており、その人々がいる場所が内側になる、という考えからと言われています。