篠津地域開発の歴史
篠津地域開発の歴史
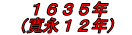
松前藩によって見い出された当時の石狩川流域は熊笹が茂り熊の出没する密林でした。 内陸は融雪と降雨による洪水のため、湿地の泥炭原野でした。
-
 開発前の篠津原野
開発前の篠津原野
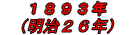
北垣北海道庁長官により篠津運河(現:篠津幹線用排水路)計画が提案されました。

この年から昭和初期にかけて運河の掘削が行われましたが、泥炭地特有の浮き上がりや法面崩れが起き、苦労の連続でした。
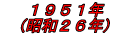
国営かんがい排水事業が土地利用を畑として面積16,519ha、事業費9億2849万2千円で始まりました。
-
 エキスカベーターによる運河の掘削状況(昭和27年頃)
エキスカベーターによる運河の掘削状況(昭和27年頃)※エキスカベーターとは多数のバケットを取り付けたホイールを回転させて、連続的に土砂の堀削を行う機械です。
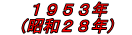
畑より水田としての利用の方が望ましいとの結論から「石狩川水域泥炭地開発計画」が提案されました。
-
 世界銀行農業調査団による石狩泥炭地開発事業の調査 (昭和29年)
世界銀行農業調査団による石狩泥炭地開発事業の調査 (昭和29年)
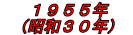
世界銀行の融資や余剰農産物見返資金の対象となり 「篠津地域篠津泥炭地開発事業」として本格的な整 備が始まりました。
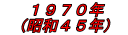
19年の歳月と217億円の巨費を投入して行われた事業 が、ようやく完了を迎えました。
-
 工事中の篠津幹線用水路
工事中の篠津幹線用水路
-
 篠津幹線用水路(通称:篠津運河)
篠津幹線用水路(通称:篠津運河)