国道で一番最初につくられた橋は どこですか?
ページ内目次
国道で一番最初につくられた橋は どこですか?
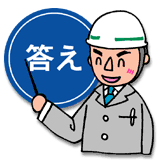
日本は、大小の河川や湖沼が多い地形なため、昔から数多くの橋がつくられてきました。記録に現れる最古の橋は、仁徳天皇の時代(西暦324年)に猪甘津橋が、今の大阪にあったことが日本書紀に記されていますし、6、7世紀につくられたとみられる木橋の遺跡が近畿地方で発見されています。石造りの橋は、長崎の眼鏡橋が江戸時代(西暦1634年)に最初につくられてから九州地方を中心に次々とつくられています。今日みられるような鋼材などでつくられた橋は、明治時代に入ってヨーロッパから技術が導入されてからです。 現在もりっぱに使われている橋(橋長が15メートル以上)で古い橋は、次のとおりです。
| 順位 |
建設年次
|
路線名
|
橋梁名
|
橋長
|
場 所
|
| 1 |
明治21年
|
34号
|
湯野田橋
|
15メートル
|
佐賀県藤津群嬉野町 |
| 2 |
明治36年
|
442号
|
小岩戸橋
|
18メートル
|
大分県大分郡津野原町 |
| 3 |
明治44年
|
1号
|
日本橋
|
49メートル
|
東京都中央区 |