基本的な考え方8
基本的な考え方
肯定的な主な意見
- 下流域の漁業や魚類の生息環境に配慮しながら、サンルダムの建設を進めてほしい。
懸念を示す主な意見
- サンルダムは、サクラマスの生息環境に大きな影響を与えるのではないですか。
- 既設ダムによるサクラマスの生息環境への影響を検証するべきではないでしょうか。
基本的な考え方
サクラマスは天塩川流域の広い範囲において生息を確認しています。また、既存資料及び現地調査結果からサクラマスの産卵可能域を推定した結果、天塩川流域の広い範囲にサクラマスの産卵可能域が分布し、あわせてサクラマス幼魚(ヤマメ)の生息が確認されています。サンル川流域で行った調査では、サクラマスの産卵床は、サンル川本川や支川など広い範囲で確認され、貯水池となる箇所以外にも多くの産卵床が確認されていることから、ダム地点において遡上・降下の機能を確保することにより、サクラマスの生息環境への影響を最小限に抑えるよう取り組むこととしています。
-
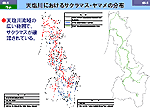 天塩川におけるサクラマス・ヤマメの分布
天塩川におけるサクラマス・ヤマメの分布
-
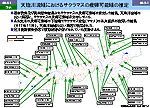 天塩川流域におけるサクラマスの産卵可能域の推定
天塩川流域におけるサクラマスの産卵可能域の推定
-
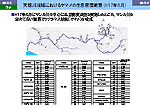 天塩川流域におけるヤマメの生息密度調査(H17年6月)
天塩川流域におけるヤマメの生息密度調査(H17年6月)
- 天塩川におけるサクラマス・ヤマメの分布 (PDF:269KB)
- 天塩川流域におけるサクラマスの産卵可能域の推定 (PDF:468KB)
- 天塩川流域におけるヤマメの生息密度調査(H17年6月) (PDF:118KB)
-
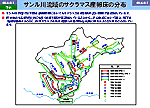 サンル川流域のサクラマス産卵床の分布
サンル川流域のサクラマス産卵床の分布
-
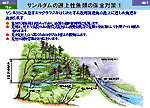 サンルダムの遡上性魚類の保全対策(1)
サンルダムの遡上性魚類の保全対策(1)
-
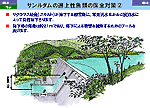 サンルダムの遡上性魚類の保全対策(2)
サンルダムの遡上性魚類の保全対策(2)
沙流川流域では平成2年からサクラマスに関する調査を実施しています。その結果、沙流川流域におけるサクラマス幼魚(ヤマメ)の生息数の推移は図-4のとおりで、以下の示す理由により年や支川により大きく異なっていますが、二風谷ダムの魚道(延長:約183メートル、落差:約11~17メートル)運用開始後も、年や支川によっては多数のヤマメが確認されています。よって、設置した魚道が機能しており、二風谷ダムによってサクラマスが減少していることはないと考えています。
具体的には、魚道運用開始後に遡上した親魚に由来する平成9年におけるサクラマス幼魚の生息数は多数であり、魚道が機能したものと考えられます。また、平成10年の生息数は前年に比べて大きく減少していますが、これは前年の二度にわたる出水の影響を受けたものと考えられます。更に、平成14、16年の生息数についても前年に比べて少数となっていますが、これはダムの上流と同様に下流の支川流域でも少なくなっていることから、それぞれ前年の平成13、15年の大規模な出水の影響を受けたためと考えられます。
-
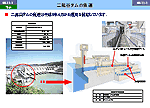 二風谷ダムの魚道
二風谷ダムの魚道
-
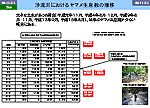 図-4 沙流川におけるヤマメ生息数の推移
図-4 沙流川におけるヤマメ生息数の推移
-
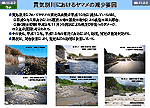 貫気別川におけるヤマメの減少要因
貫気別川におけるヤマメの減少要因
美利河ダムは、平成4年度から供用され、当初は魚道を未設置であったものの、河川環境を保全するため、魚道(延長:約2.4キロメートル、落差:約34メートル)が計画され、平成17年度から魚道が運用されています。平成17年度の魚類調査ではサクラマスをはじめ、アメマス、ヤマメ、ウグイ等が確認されており、引き続きモニタリングを続ける予定です。
-
 美利河ダムの魚道(1)
美利河ダムの魚道(1)
-
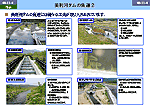 美利河ダムの魚道(2)
美利河ダムの魚道(2)
-
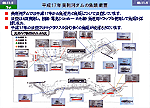 平成17年美利河ダムの魚類調査
平成17年美利河ダムの魚類調査
アメリカのコロンビア川流域には、サケ・マス類を対象とした高さ約21メートル~約34メートルの魚道が河口から約230キロメートル~約700キロメートル上流のダムに設置されています。図-5に示すとおり、魚道の効果が確認されています。
-
 コロンビア川流域のダム群(1)
コロンビア川流域のダム群(1)
-
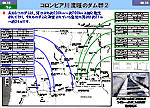 コロンビア川流域のダム群(2)
コロンビア川流域のダム群(2)
-
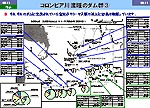 コロンビア川流域のダム群(3)
コロンビア川流域のダム群(3)図-5 魚道を遡上したサケ・マス類の確認数