官庁営繕 Q6
ページ内目次
Q6:「耐震安全性」とは何ですか?
| A6: | |
| 官庁施設の多くは、地震災害時に、応急復旧や復興等の防災機能を果たす防災拠点としての役割があります。 また、災害時の素早い行政サービス回復のため、施設の用途に応じた耐震安全性の目標を定めています。 |
用途に応じた耐震安全性の目標
| 施設の用途 | 対象施設 | 目標 |
|---|---|---|
| 災害対策の指揮、情報伝達等のための施設 | 災害対策基本法で指定された特に重要度の高い施設 | I 類 |
| 災害対策基本法で指定された上記以外の施設 | II 類 | |
| 被災者の救助、救急医療活動、消火活動等のための施設 | 災害時に拠点して機能すべき病院、消防関係施設 | I 類 |
| 上記以外の病院、消防関係施設 | II 類 | |
| 非難所として位置づけられた施設 | 学校、研修施設のうち、避難所として指定された施設 | II 類 |
| 危険物を貯蔵又は使用する施設 | 放射性物質又は病原菌類を取リ扱う施設 | I 類 |
| 石油類、高圧ガス、毒物等を取リ扱う施設 | II 類 | |
| 多数の者が利用する施設 | 文化施設、学校施設、社会教育施設等 | II 類 |
| その他 | 一般官庁施設 | III類 |
| I 類 | 大地震動後、構造体の補修の必要がなく使用出来、人命の安全、十分な機能確保 |
| II 類 | 大地震動後、構造体の大きな補修がなく使用出来、人命の安全、機能確保 |
| III類 | 大地震動後、構造体の部分的な損傷は生じるが耐力の低下は著しくなく、人命の安全確保 |
また、既存の建築物で目標の耐震安全性が確保できない場合、耐震補強工事を行うものもあります。
| ■耐震改修(補強)とは 建物の耐震性能を向上させることを耐震補強といいます。補強構法によってその効果は異なります。 |
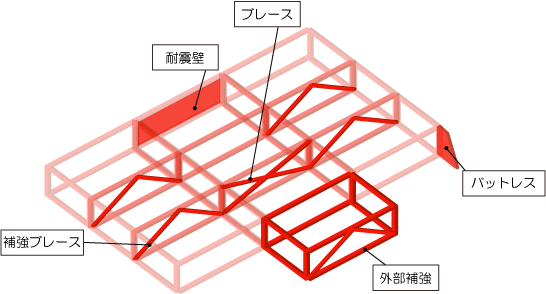 |
| ■補強方法 ・建築物の耐力を上げる方法(耐力向上) ・ねばり強くさせる方法(靱性改善) ・建築物の地震時挙動を制御する方法(応答制御・入力低減) |
■補強方法の比較
|
種別
|
耐震補強
|
制震補強
|
免震補強
|
|
目的
|
地震力に抵抗 | 地震エネルギーの吸収により地震力の低減 | 地震入力をかわし地震力の大幅低減 |
|
手段
|
強度抵抗部材の配置靱性改善 | エネルギー吸収装置(ダンパ)の配置 | 免震装置の配置 |
|
部材
|
強度抵抗:壁、ブレース、フレーム増設等 靱性改善:繊維補強、スリット等 |
弾塑性ダンパ オイルダンパ |
積層ゴム、滑り支承(ベアリングの役割を果たすもの) |
|
特徴
|
耐力不足や高い安全性の確保の程度に 応じて補強構面が増大 |
耐震補強に比較して、補強構面が少ない | 高い耐震安全性や機能維持確保が可能 |
|
工事量
|
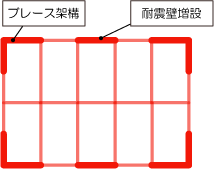 補強構面多 |
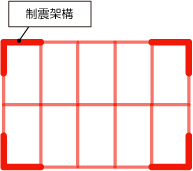 補強構面少 |
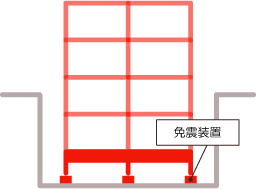 免震層に工事集約 |
