川づくりの歴史
川づくりの歴史
北海道の川づくりの歴史は、明治の開拓期から始まります。
現在は、ショートカット工事や堤防整備、ダムなどにより洪水の危険は少なくなりましたが、近年も洪水被害は多く発生しています。
また、環境に対する社会的ニーズが高まっていることから「環境と調和した川づくり」が求められています。
現在は、ショートカット工事や堤防整備、ダムなどにより洪水の危険は少なくなりましたが、近年も洪水被害は多く発生しています。
また、環境に対する社会的ニーズが高まっていることから「環境と調和した川づくり」が求められています。
洪水に苦しめられた開拓民

しかし、明治31年にこの新天地をおそった未曾有の大洪水は、人々の家屋、切り開かれたばかりの田畑、さらに尊い人命までも濁流の渦へと巻き込みました。
岡崎博士の治水計画
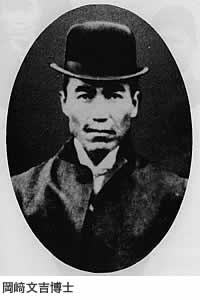
ショートカット工事の推進
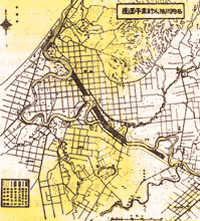
堤防などの河道整備とダム建設

頻発する洪水被害を軽減するため、堤防整備やショートカット工事などを戦前に引き続き進めるとともに、治水と農業用水、発電等の役割を兼ねた多目的ダムを建設するなど、戦後の復興を支えました。
環境と調和した川づくり

そのことから、北海道開発局では、整備にあたっては「多自然型川づくり」や「自然再生事業」などにより、環境と調和した川づくりを進めています。
石狩川の歴史についてはこちらをご覧ください
