道路特定財源制度
道路特定財源制度

道路特定財源制度
道路特定財源制度は、我が国の立ち遅れた道路を緊急かつ計画的に整備するために、自動車利用者にお願いして、燃料の消費、自動車の取得、保有に対して適正な税負担を求め、国及び地方の道路整備の財源とする制度です。
道路特定財源一覧
| 車種 | 燃料の消費 | 自動車の購入 | 自動車の保有 |
|---|---|---|---|
| ガソリン車 |
ガソリン税 ・揮発油税(国の財源) ・地方道路税(地方の財源) |
自動車取得税 (地方の財源) |
自動車重量税※ (国・地方の財源) |
| 軽油車 | 軽油引取税(地方の財源) | ||
| LPG車 | 石油ガス税(国・地方の財源) |
※自動車重量税は形式上は一般財源ですが、税創設などの経緯から道路特定財源として扱われています。
受益と負担の関係
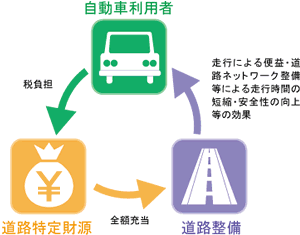
道路特定財源制度は、「受益者負担」「損傷者負担」という理念に基づくシステムであり、利用者の目からみても、次のような長所をもっています。
•自動車利用者が便益に応じた道路整備費用を負担する公平性
•税負担が確実に道路整備に充てられ、利用者に還元されるという合理性
•計画的な道路整備のために必要な財務を安定的に確保できる安定性
※昨年、小泉総理大臣の指示に基づき、12月9日に政府・与党において、「道路特定財源の見直しに関する基本方針」がとりまとめられました。これに基づき、今年の歳出・歳入一体改革の議論の中で、道路特定財源の見直しの検討を進めることとされています。
「道路特定財源」についてもっと知りたい方は
