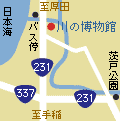川の防災ミュージアム 石狩地区地域防災施設(川の博物館)
見学をご希望の方へ
お申し込み先
札幌開発建設部 札幌河川事務所
電話:011-581-3207
電話:011-581-3207
石狩地区地域防災施設(川の博物館)
■住所:石狩市新港南1丁目28-24
■交通:バス→札幌中央バスターミナルから中央バス「石狩」行きで40分、「6線」下車、徒歩4分
車→札幌北ICからおよそ20分
■交通:バス→札幌中央バスターミナルから中央バス「石狩」行きで40分、「6線」下車、徒歩4分
車→札幌北ICからおよそ20分
石狩川(いしかりがわ)放水路の近くにある「川の博物館」は、昭和60年、災害時には地域の防災拠点となる石狩川の治水資料館として開館しました。洪水などから私たちの生活を守り、産業をささえ、水を大切に利用するために行うのが治水事業(ちすいじぎょう)です。館内には、石狩川の治水事業に関係したパネルなどが展示されています。
流域の人々を恐ろしい水害から守る頼もしい「石狩川放水路」
2階が展示室、3階が石狩川放水路管理センターとなっています。「石狩川放水路」とは、文字通り、水を流す路(みち)のこと。石狩川の支流の一つ、茨戸(ばらと)川と日本海の間に放水路をつくり、洪水などで茨戸川の水位が上がると放水路を開き、川の水を直接日本海に流します(くわしくは、「石狩川治水史」を見てください)。
いつもはゆったりと流れている川も、大雨や台風などで一定の水量をこえるとあふれ出し、周辺の地域に被害を及ぼしてしまいます。そんな災害の発生を防ぎ、いつでもおだやかに流れる川にするのが放水路です。
いつもはゆったりと流れている川も、大雨や台風などで一定の水量をこえるとあふれ出し、周辺の地域に被害を及ぼしてしまいます。そんな災害の発生を防ぎ、いつでもおだやかに流れる川にするのが放水路です。
-

さまざまなイメージの水の映像が映し出されている「テレビ万華鏡」。頭を入れてのぞいてみるとおもしろいよ。
-

伏籠川の周辺を洪水から守るための「伏籠川総合治水対策」
都市化が進んで地面がアスファルトでおおわれると、雨水は地面にしみ込まず、短い時間に多くの水が川へ流れ出してしまいます。そのため、流域内で水を貯めたり、しみ込ませたり、総合的な治水を行うことが必要です。
伏籠川(ふしこがわ)総合治水対策コーナーでは、周辺の地域を水害から守るために行われているさまざまな事業について、パネルで説明しています。
伏籠川(ふしこがわ)総合治水対策コーナーでは、周辺の地域を水害から守るために行われているさまざまな事業について、パネルで説明しています。
-

-
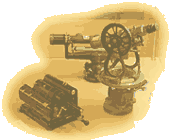
当時使われていた計測器なども展示されています。
-

-

ポンプ浚渫船(しゅんせつせん)/対象8年~現在 水中の土砂をカッターで切りくずし、吸い上げる機械。現在も石狩川下流の河道拡幅にかつやくしています。
石狩川治水の祖・岡崎文吉
石狩川の治水の歴史は、明治時代にまでさかのぼります。岡崎文吉は、「石狩川治水の祖(そ)」と呼ばれる人物。彼の考え出した自然を大切にした治水は、今日の事業にも活かされています。
「岡崎文吉の紹介コーナー」では、「岡崎式単床(たんしょう)ブロック」とよばれるコンクリートブロックや捷水路(しょうすいろ)の実施などについて展示していますので、ぜひのぞいてみてください。
「岡崎文吉の紹介コーナー」では、「岡崎式単床(たんしょう)ブロック」とよばれるコンクリートブロックや捷水路(しょうすいろ)の実施などについて展示していますので、ぜひのぞいてみてください。
「地域の防災拠点」としての活用
地域住民、防災関係者等を対象に水害によるDIG(災害図上訓練)、石狩川放水路の施設説明会、災害セミナー等を行っており防災教育の場となっています。