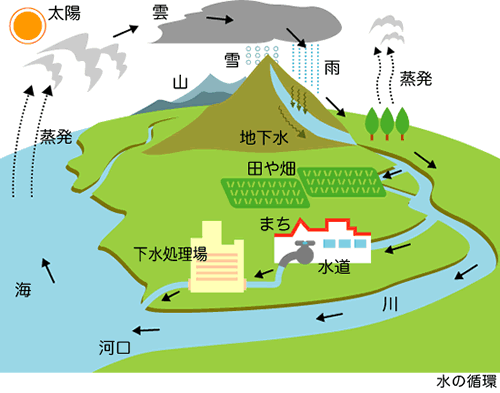第1部:川の生い立ち
川の生い立ち

川の水はどこから来るの?

川の水は、山や平野に降った雨が集まったものです。その川の水は海へと流れ、温められると蒸発して水蒸気になり、空の上で雲になります。その雲が雨を降らせ、再び川の水になるのです。
このように、水はいろいろな姿に変わります。これを「水の循環(じゅんかん)」と呼びます。川は水の循環の一部なのです。川になるまで、水はいろいろ姿を変えて冒険しているんですね。

川の始まりと終わりはどこ?

川を上流へ向かってのぼって行くと、ところどころで「わき水」が流れ出ていたり、小さな「泉」があったりします。これが川の始まりです。ですから、始まりは1ヵ所とは限りません。
さて、川の終わりですが、地質学では海岸線に口を開く「河口」を川と海の境としています。また、海図上では河口からさかのぼって「最初の橋」までを海、橋よりも上流を川としています。

どうして川の水はなくならないの?

山に降った雨は地面に落ち、少しずつ土の中にしみこんでいきます。しみこんだ水は木の根に吸われたり、土のすき間にたくわえられたりしながら、下へ下へとしみこんでいき、水を通しにくい地層の上にたまります。こうしてたまった水を「地下水」といいます。
この地下水が、地層の境目や割れ目などから自然にわき出ているものが「わき水」です。わき水は急になくなることはなく、少しずつ川へと流れこんでいるので、雨が降らなくても川の水がなくならないのです。

大きな川はどうやってできるの?

川の上流はわき出たばかりの小川ですが、流れていく途中でいくつも集まり、少し大きな川になります。この川は途中で山をけずり、土や砂を押し流していろいろな地形をつくりながら、海や湖に向かって流れていきます。
さらに、そうした川が集まって、もっと大きな川が誕生します。平野をゆうゆうと流れる大きな川は、小さな川たちがみんなで集まった姿なのです。