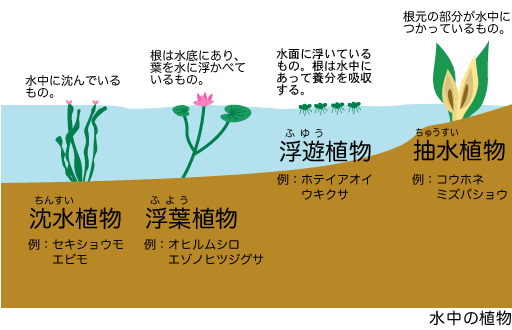第3部:川の生態
川の生態

川の中にはどんな草が生えているの?

水中や水辺で育つ植物を「水生植物(すいせいしょくぶつ)」といいますが、水生植物は川の水中にある栄養分を吸収してくれるので、水をきれいにするという大きな役割を果たしています。また、水生植物の周りには多くの微生物(びせいぶつ)がいて、それをエサにする小さな生物が集まり、またそれをエサに魚や鳥が集まってきます。さらに魚のかくれ場所や産卵場所にもなり、水中の生物の世界ではとても重要な役割があるのです。
水生植物の種類は、流れの速さや水の深さ、水質、底が泥か砂かなどによっていくつかの種類に分けることができます。一般には、水がよどんだ場所や、流れのゆるやかな場所に多く見られます。

川にはどんな虫がいるの?

昆虫の中で、水中で生活しているものを「水生昆虫(すいせいこんちゅう)」といいます。水生昆虫とは、「少なくとも一生のある期間、水の中に住む昆虫」のことで、チョウの仲間、カブトムシの仲間というように虫の形で区別されたのではなく、すんでいる場所からつけられた昆虫のよびかたです。ですから、陸に上がった昆虫が再び水中に入ったものも、水生昆虫の仲間です。水生昆虫は海水や汽水(きすい:海水と淡水の混ざったところ)にすむものもいますが、ほとんどの種類は川・湖・池・水田といった淡水(たんすい:塩分を含まない水)にすんでいます。
淡水は、湖・池・水田などの流れのないところ(止水)と、川のように流れのあるところ(流水)に大きく分けられます。止水には、トンボ、ゲンゴロウ、ミズスマシ、アメンボ、ミズカマキリ、タイコウチといった昆虫がすんでいて、昔はなじみの深いものでしたが、近年は数が減りつつあります。流水には、カゲロウ、カワゲラ、トビケラ、ヘビトンボといった昆虫がすんでいます。小さくて見分けるのがむずかしいけれど、きれいに流れる川の底や石の裏をよく見てみると、元気に動きまわる虫たちの姿を見ることができますよ。

川にはどんな魚がいるの?

川の魚を生態で分けると、フナのように一生を淡水で過ごす「純淡水魚(じゅんたんすいぎょ)」や、アユやハゼ類のように川で生まれ、海に下って再び淡水にもどる「両側回遊魚(りょうそくかいゆうぎょ)」、サケやマスのように川で生まれて海に下り、産卵のために淡水にもどる「遡河回遊魚(そかかいゆうぎょ)」、ウナギのように産卵のために海にもどる「降河回遊魚(こうかかいゆうぎょ)」がいます。また、川の上流から下流まで、さまざまな魚が「すみ分け」をしています。

川にはどんな鳥がやって来るの?

鳥も魚と同じく、それぞれ自分のすみやすい環境を見つけて暮らしています。流れの急な上流にすむ鳥は、群れをつくりません。また、声の美しいアカショウビンや川の中を歩くカワガラスなど、めずらしい習性の鳥が多いのも特徴です。
中流は、魚が大好物のカワセミやハクセキレイ、キセキレイたちの食堂。ダイビングしたり、待ち伏せしたりとエサの取り方もいろいろです。下流では、ヨシ原に巣を作るコヨシキリ、水辺でエサを取るサギの仲間、河口にはカモやカモメなどさまざまな鳥たちがやってきます。
※このほかどんな生き物がすんでいるのか、「川で遊び学ぼう」でも詳しく説明しています。