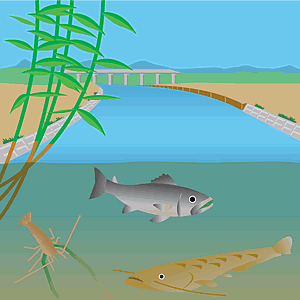下流
川で遊び学ぼう
川の終着点「下流」
川のゴールである海に近くなると、流れは一段と遅くゆるやかになり、水量も豊かになって川幅が広くなります。川底には、上流から運ばれてきた小石や砂、泥などがたまり、河口付近では「三角州(さんかくす)」ができます。
また、洪水のたびに泥などがたまって、川の両側に自然の堤防(ていぼう)ができることがあります。この堤防のため、洪水(こうずい)が終わっても水は川に戻ることができず、小さな沼や湿地をつくることがあります。こうしてできた沼や湿地の多くは、水田などに利用されてきました。
都市部では、洪水を防ぐほか、田畑に水を入れるために、人工の放水路や堤防が作られています。
また、洪水のたびに泥などがたまって、川の両側に自然の堤防(ていぼう)ができることがあります。この堤防のため、洪水(こうずい)が終わっても水は川に戻ることができず、小さな沼や湿地をつくることがあります。こうしてできた沼や湿地の多くは、水田などに利用されてきました。
都市部では、洪水を防ぐほか、田畑に水を入れるために、人工の放水路や堤防が作られています。
-
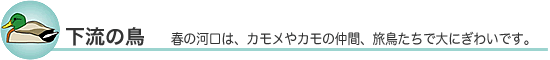
-

ハクセキレイ
ハクセキレイ セキレイ科/全長約20センチメートル
川や湖などの水辺、畑、市街地などで、とてもよくみかける鳥。チチッと鳴きながら波形に飛ぶ。岩の割れ目に巣を作り、水辺の虫を食べる。
川や湖などの水辺、畑、市街地などで、とてもよくみかける鳥。チチッと鳴きながら波形に飛ぶ。岩の割れ目に巣を作り、水辺の虫を食べる。
-

イソシギ
イソシギ シギ科/全長20センチメートル
尾をふる仕草が目立つ小型のシギ。ツー、チー、チーとよく通る声で鳴く。春に川原に渡ってきて、草地に巣を作る。シギやチドリのなかまは、敵が近づくと、親鳥がつばさをばたつかせて注意をひき、ヒナを救う。
そのほか
マガモ ガンカモ科 キアシシギ シギ科 カルガモ ガンカモ科
尾をふる仕草が目立つ小型のシギ。ツー、チー、チーとよく通る声で鳴く。春に川原に渡ってきて、草地に巣を作る。シギやチドリのなかまは、敵が近づくと、親鳥がつばさをばたつかせて注意をひき、ヒナを救う。
そのほか
マガモ ガンカモ科 キアシシギ シギ科 カルガモ ガンカモ科
-
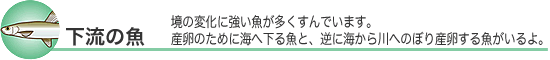
-

ウキゴリ
ウキゴリ ハゼ科/全長約13センチメートル
流れのゆるやかな場所にすむハゼのなかま。平らな石の下などを掘って巣を作り、メスが産卵 したあと、オスが卵を守る。
そのほか
ワカサギ キュウリウオ科 コイ コイ科
流れのゆるやかな場所にすむハゼのなかま。平らな石の下などを掘って巣を作り、メスが産卵 したあと、オスが卵を守る。
そのほか
ワカサギ キュウリウオ科 コイ コイ科
-
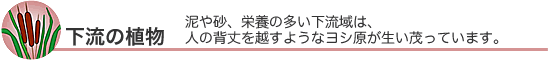
-

ナガバヤナギ
-
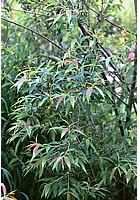
タチヤナギ
-

エゾノカワヤナギ
ヤナギ類 ヤナギ科
いろいろな種類があり、岸辺に生えて林をつくる。荒れ地にも育つ力が強く、川原の 植樹活動にもよく植えられる。
そのほか
ガマ ガマ科 フトイ カヤツリグサ科 ヨシ イネ科
写真撮影 鳥:日本野鳥の会 北海道支部
魚:中村文彦さん・三沢勝也さん
植物:佐藤孝夫さん
いろいろな種類があり、岸辺に生えて林をつくる。荒れ地にも育つ力が強く、川原の 植樹活動にもよく植えられる。
そのほか
ガマ ガマ科 フトイ カヤツリグサ科 ヨシ イネ科
写真撮影 鳥:日本野鳥の会 北海道支部
魚:中村文彦さん・三沢勝也さん
植物:佐藤孝夫さん