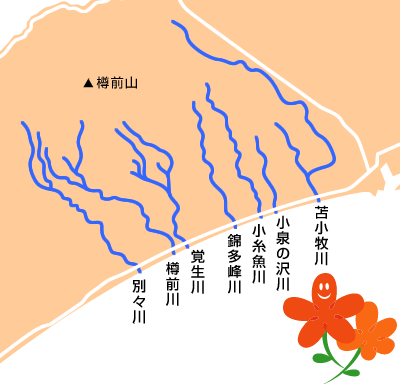噴火対策工事計画
安全のため、自然と街がともに生きていくために、いろいろな工夫をしています。
樽前山から流れる7つの川で、噴火の被害(ひがい)をできるだけ小さくするため、砂防施設(さぼうしせつ)をつくる工事を計画(けいかく)しています。
工事をする時には、人が、美しい自然、そして貴重な動植物とともに生きていくため、いろいろな工夫をしています。
工事をする時には、人が、美しい自然、そして貴重な動植物とともに生きていくため、いろいろな工夫をしています。
どんな工夫をしているの?

●それぞれの川のまわりを調査(ちょうさ)し、その土地にあわせた計画を立てるようにしています。
●施設をつくる時には、できるだけまわりの木を切らないで自然を残すようにしています。
●木を切らなければならない時は、在来種(ざいらいしゅ)の木を植えて、元にもどすようにしています。
●魚の道である川を止めたり段差をつけたりしていません。
●施設をつくる時には、できるだけまわりの木を切らないで自然を残すようにしています。
●木を切らなければならない時は、在来種(ざいらいしゅ)の木を植えて、元にもどすようにしています。
●魚の道である川を止めたり段差をつけたりしていません。
覚生川(おぼっぷがわ)では3号遊砂地(ゆうさち)が完成しました。
樽前山のふもとを流れる覚生川(おぼっぷがわ)、錦多峰川(にしたっぷがわ)では、セルと呼ばれる砂防施設をつくる工事が行われ、遊砂地(ゆうさち)が完成しました。
セルの上には森や林ができる
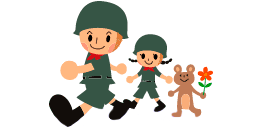
●セルをおいた場所には土をかぶせるので、その上にはまた木や草が生えてきます。
●自然にまかせるだけでなく、人の力でもまわりの森にあった木を植えています。