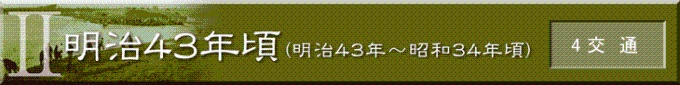明治43年頃-交通5【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌
明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 4交通
いよいよ空の玄関が開かれた
千歳空港のはじまり
千歳市の土壌は『樽前山』の噴火がもたらした火山灰などに覆われ、作物がなかなか育たなかった。まちでは、「広大な土地を軍用飛行場にしては」という話が持ち上がった。それが実現に向けて動き出すのは、大正15年のことだ。
千歳駅が開業し、鉄道を利用して千歳市で観楓会を催すことにした小樽新聞社(現・北海道新聞社)に、まちも食事をふるまうことを決めると、そのお礼に、汽車が千歳駅に到着する時に飛行機を飛ばして、空から宣伝ビラをまくことになった。まちでは飛行機を住民に見せるため、離発着場をつくることにし、2日間にわたって住民が総出で整地した。こうして、長さ約200m、幅約110m、面積7,500坪の着陸場が完成した。
昭和12年に千歳市が航空基地に決まり、戦時中は北海道の空の基地として重要な役割を担った。終戦後は連合軍に使用されたが、その間、連合軍は滑走路を延長するなど近代施設になり、羽田空港をもしのぐ第一級の飛行場になっていった。 昭和26年には「東京~札幌間」に定期航空路が就航し、民間初の飛行機「もく星号」が大歓迎の中、千歳に到着したのだ。
*参考資料/「新北海道史第一巻概説」「千歳航空協会・空港の歴史」より
千歳駅が開業し、鉄道を利用して千歳市で観楓会を催すことにした小樽新聞社(現・北海道新聞社)に、まちも食事をふるまうことを決めると、そのお礼に、汽車が千歳駅に到着する時に飛行機を飛ばして、空から宣伝ビラをまくことになった。まちでは飛行機を住民に見せるため、離発着場をつくることにし、2日間にわたって住民が総出で整地した。こうして、長さ約200m、幅約110m、面積7,500坪の着陸場が完成した。
昭和12年に千歳市が航空基地に決まり、戦時中は北海道の空の基地として重要な役割を担った。終戦後は連合軍に使用されたが、その間、連合軍は滑走路を延長するなど近代施設になり、羽田空港をもしのぐ第一級の飛行場になっていった。 昭和26年には「東京~札幌間」に定期航空路が就航し、民間初の飛行機「もく星号」が大歓迎の中、千歳に到着したのだ。
*参考資料/「新北海道史第一巻概説」「千歳航空協会・空港の歴史」より
-
 千歳初の旅客機が羽田と千歳を往復(陸軍航空大演習)
千歳初の旅客機が羽田と千歳を往復(陸軍航空大演習)
-
 小樽新聞社機「北海」第一号 (海軍10年式艦上偵察機の民間改造型)(千歳市蔵)
小樽新聞社機「北海」第一号 (海軍10年式艦上偵察機の民間改造型)(千歳市蔵)