開拓初期:千歳川流域-産業【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
開拓初期(明治初期~明治42年頃) 千歳川流域 産業
〈開拓初期の産業の状況〉
恵庭は江戸時代に伐木が盛んに行われた。場所請負人の飛騨屋久兵衛は松前藩の許可を受け、漁川上流の空沼岳などで木を伐採し、流送で漁川から千歳川を経由して石狩川河口まで運び、石狩湾から本州に運んだ。明治になると、薪炭(しんたん・木を原料にした燃料)が千歳の大きな産業になり、生産された薪炭は川船で千歳川を下って江別に出荷された。
またサケが遡上する千歳川では、今や世界一ともいわれる北海道のサケふ化事業の歴史が開かれた。
江別には当時、川の港と鉄道駅があり、流送と舟運、そして鉄道をむすぶ道央の物流の拠点だった。この環境を活かして、製紙会社が大工場を建設した。また野幌では、レンガ工場が相次いで操業をはじめ、江別を代表する地場産業に成長していく。
またサケが遡上する千歳川では、今や世界一ともいわれる北海道のサケふ化事業の歴史が開かれた。
江別には当時、川の港と鉄道駅があり、流送と舟運、そして鉄道をむすぶ道央の物流の拠点だった。この環境を活かして、製紙会社が大工場を建設した。また野幌では、レンガ工場が相次いで操業をはじめ、江別を代表する地場産業に成長していく。
100年におよぶ人工ふ化事業
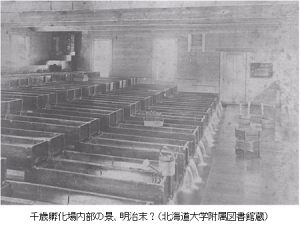
遡上するサケの親魚を水車に導き、すくい揚げて捕獲する捕魚車は、伊藤一隆により紹介され、明治29年に採卵場が現在の千歳橋上流に移転された際に導入された。30年にはさらに下流の根志越に移され、改良が重ねられて今の形になった。そして平成6年の「千歳サケのふるさと館」オープンにあわせ、今の花園地区 に設置された。「インディアン水車」と呼ばれるようになるのは、昭和46年頃からという。
*参考資料/新千歳市史、千歳サケのふるさと館「インディアン水車設置の歴史」
-
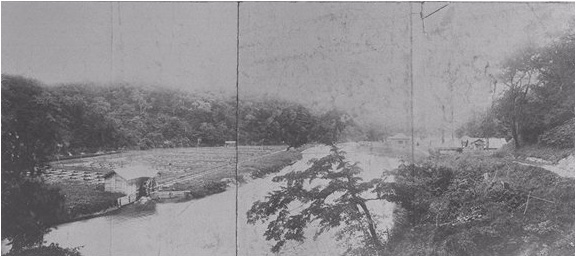 千歳孵化場遠景、明治末?
千歳孵化場遠景、明治末?(北海道大学附属図書館蔵)
