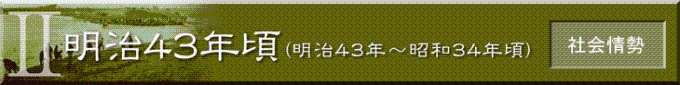明治43年頃-社会情勢1【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌
明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 社会情勢
<この時代に進められた政策>
・第1期拓殖計画(明治43~昭和元年)
・第2期拓殖計画(昭和2~21年)
・戦後緊急開拓(昭和22~26年)
・第1期総合開発計画
(第一次五ヶ年実施計画 昭和27~31年)
・第1期拓殖計画(明治43~昭和元年)
・第2期拓殖計画(昭和2~21年)
・戦後緊急開拓(昭和22~26年)
・第1期総合開発計画
(第一次五ヶ年実施計画 昭和27~31年)
1 石狩川治水のはじまり

(札幌写真ライブラリー蔵)
2 戦争の影響
北海道の開拓は、戦争によって一進一退する。
(1)第一次世界大戦 大正3年(1914年)
経済不況で北海道開拓も足踏み状態の時、この大戦が起こり、農業が開拓以来の活況になるなど、北海道は未曾有の好景気をむかえた。しかし大戦後は一転して大恐慌になり、長引く不況に苦しめられた。
(2)満州事変 昭和6年(1931年)
軍需が増えて産業は発達した。北海道では、昭和11年に対ソ連軍(現在のロシア)を想定した『陸軍特別大演習』が初めて行われることになり、道路工事など土木建設と交通網の整備が進んだ。
(3)日中戦争~太平洋戦争 昭和12年(1937年)
戦いは長期化し、第二次世界大戦の戦局のひとつ「太平洋戦争」(昭和16年~20年)に突入し、徴兵が行われ統制は厳しさを増した。軍需景気が一時的に経済を刺激するものの、戦局の悪化とともに産業も暮らしも疲弊していき、国土は荒廃した。
(1)第一次世界大戦 大正3年(1914年)
経済不況で北海道開拓も足踏み状態の時、この大戦が起こり、農業が開拓以来の活況になるなど、北海道は未曾有の好景気をむかえた。しかし大戦後は一転して大恐慌になり、長引く不況に苦しめられた。
(2)満州事変 昭和6年(1931年)
軍需が増えて産業は発達した。北海道では、昭和11年に対ソ連軍(現在のロシア)を想定した『陸軍特別大演習』が初めて行われることになり、道路工事など土木建設と交通網の整備が進んだ。
(3)日中戦争~太平洋戦争 昭和12年(1937年)
戦いは長期化し、第二次世界大戦の戦局のひとつ「太平洋戦争」(昭和16年~20年)に突入し、徴兵が行われ統制は厳しさを増した。軍需景気が一時的に経済を刺激するものの、戦局の悪化とともに産業も暮らしも疲弊していき、国土は荒廃した。
3 北海道総合開発時代へ

(砂川捷水路。石狩川振興財団蔵)
それは、『石狩川水系総合開発事業』を大きな柱にした、地域の総合的な開拓だった。食糧増産では、未開発だった泥炭地を農地にする、巨大プロジェクトが石狩川流域で進められた。