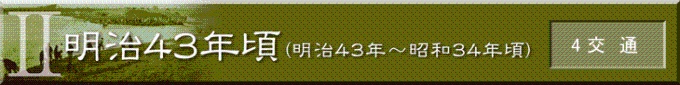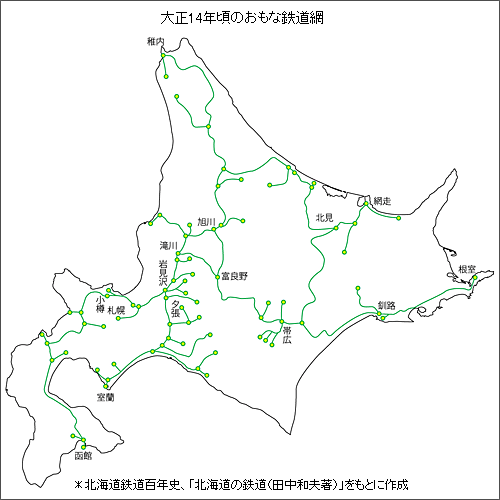明治43年頃-交通2【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌
明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 4交通
北海道を網羅し山奥を走る鉄道
東西南北を貫く鉄道網の完成

路線では、「函館線(函館本線、幌内、歌志内、手宮ほか)」「室蘭線(室蘭本線、万字、夕張線)」「留萌線」「釧路線」などが開通し、大正10年には「根室線」が開通して北海道横断線が、翌11年には宗谷線が開通して北海道縦貫線が完成し、そこから重要な支線が開かれていった。
鉄道網の発達は、開拓推進の原動力になった。
*参考資料/新北海道史第一巻概説より
山奥に森林鉄道の汽笛が響く
木材は、川の「流送」で運ばれていたが、搬出時期や木材の種類と数量が限定され、森や川を傷め、魚類の繁殖にも弊害があるため廃止された。そして、大正8年から昭和初期にかけて、『森林鉄道』が盛んに敷設された。
簡易な鉄道で、木材を運ばない時は低運賃で住民を乗せ、山間地の農産物や生活物資も運んだため、重宝がられた。石炭を運んだこともあり、三笠市では幾春別地区と桂沢地区に敷設された。蒸気機関車は、タマネギのような煙突が特徴で、ディーゼルの登場まで活躍した。
しかし昭和30年代後半にトラック輸送が主流になり、林道も整備されると、森林鉄道は姿を消した。
*参考資料/新北海道史第五巻通説四より
簡易な鉄道で、木材を運ばない時は低運賃で住民を乗せ、山間地の農産物や生活物資も運んだため、重宝がられた。石炭を運んだこともあり、三笠市では幾春別地区と桂沢地区に敷設された。蒸気機関車は、タマネギのような煙突が特徴で、ディーゼルの登場まで活躍した。
しかし昭和30年代後半にトラック輸送が主流になり、林道も整備されると、森林鉄道は姿を消した。
*参考資料/新北海道史第五巻通説四より
石狩川流域のおもな森林鉄道
・芦別森林鉄道 ・幾春別森林鉄道 ・主夕張森林鉄道、下夕張森林鉄道 ・恵庭森林鉄道 ・定山渓森林鉄道 など
・芦別森林鉄道 ・幾春別森林鉄道 ・主夕張森林鉄道、下夕張森林鉄道 ・恵庭森林鉄道 ・定山渓森林鉄道 など