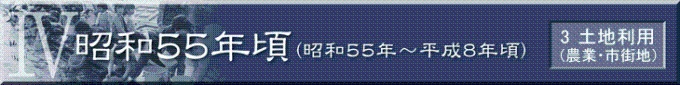昭和55年頃-土地利用2【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌
昭和55年頃(昭和55年~平成8年頃) 3土地利用(農業・市街地)
総合開発の効果と都市化による変化
進展期の土地利用
-
 きらら街道。江別市側から南幌町側を望む(北海道農政部蔵)
きらら街道。江別市側から南幌町側を望む(北海道農政部蔵)
上川盆地と石狩低地帯の水田地帯を中心に、これを取り巻くように畑作地帯が、その外側に酪農地帯が展開している。道央圏は、札幌都市圏が拡がって人口集中するのにともなって、石狩低地帯南部と周辺の山間部が野菜の供給基地となり、野菜と酪農が複合した営農体系になっている。
昭和42年から47年の土地利用図には、昭和30年代初頭に着手された「篠津泥炭地開発事業」の効果がはっきりと現れている。泥炭地を含めた石狩低地帯の中北部がほぼ水田になり、周辺の台地や緩傾斜地にまで大規模な水田がつくられた。
また、千歳~追分~夕張の火山灰地、美瑛~富良野の火砕流台地は、まとまった畑作地帯が形成された。
都市化による土地利用の変化としては、札幌市街地の拡張とともに江別市・千歳市・北広島市・恵庭市・石狩市などベッドタウンの成長が著しい。これにより、札幌圏の農地が大幅に減少し、荒地も多くなっている。石狩湾新港の開発の影響と、札幌周辺住宅地の拡張も顕著に見られる。
旭川市を中心とした地帯も、市街地拡張による農耕地の減少が顕著だ。岩見沢市・滝川市・深川市・富良野市などの地方中心都市の成長も著しい。
*参考資料/北海道開発局農業水産部農業設計課「石狩川流域の土地利用と、その展開過程」より
昭和42年から47年の土地利用図には、昭和30年代初頭に着手された「篠津泥炭地開発事業」の効果がはっきりと現れている。泥炭地を含めた石狩低地帯の中北部がほぼ水田になり、周辺の台地や緩傾斜地にまで大規模な水田がつくられた。
また、千歳~追分~夕張の火山灰地、美瑛~富良野の火砕流台地は、まとまった畑作地帯が形成された。
都市化による土地利用の変化としては、札幌市街地の拡張とともに江別市・千歳市・北広島市・恵庭市・石狩市などベッドタウンの成長が著しい。これにより、札幌圏の農地が大幅に減少し、荒地も多くなっている。石狩湾新港の開発の影響と、札幌周辺住宅地の拡張も顕著に見られる。
旭川市を中心とした地帯も、市街地拡張による農耕地の減少が顕著だ。岩見沢市・滝川市・深川市・富良野市などの地方中心都市の成長も著しい。
*参考資料/北海道開発局農業水産部農業設計課「石狩川流域の土地利用と、その展開過程」より
軌道跡を農道に活用

『空知南部広域農道(通称・きらら街道)』は、「岩見沢市栗沢~江別市野幌間」をむすぶ長い農道で、平成15年に全線が開通した。
バス路線も走り、沿道住民の重要な交通手段になっているばかりか、美しい田畑の中に『南幌温泉』や『栗ヶ丘公園(工事で発生した土砂を丘として整備)』、農産物直売所などが連なる。その中には、夕張川の旧川を活用した「北長沼水郷公園」もあるなど、南空知の農業体験ドライブコースとして人気を集めている。