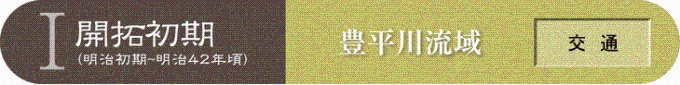開拓初期:豊平川流域-交通1【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
開拓初期(明治初期~明治42年頃) 豊平川流域 交通
〈開拓初期の交通の状況〉
開拓当初の札幌の物資輸送は、運河として利用された創成川が中心だった。当時の創成川沿いには、回漕店や倉庫群が並んでいたという。
その後幌内鉄道(小樽~三笠間)が開通し、道路では札幌本道(現・国道36号)や上川道路(国道12号)という基幹交通が発達した。対雁街道や「円山~銭函間」新道など地域間をむすぶ道路とともに、入植地に通じる道路も整備され、札幌本府を中心に道路網が形成されつつあった。
その後幌内鉄道(小樽~三笠間)が開通し、道路では札幌本道(現・国道36号)や上川道路(国道12号)という基幹交通が発達した。対雁街道や「円山~銭函間」新道など地域間をむすぶ道路とともに、入植地に通じる道路も整備され、札幌本府を中心に道路網が形成されつつあった。
札幌越新道とトヨヒラ通行屋
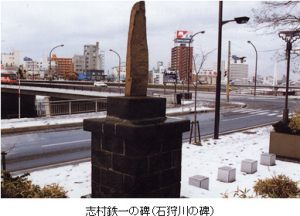
しかし明治政府に体制が変わると、志村は解雇され、付近に住んでいた吉田茂八が業務を受け継いだ。吉田は吉田掘の掘削工事も請け負い、後に創成川上流としてつなげられた。トヨヒラ通行屋は豊平橋の架橋で、その役割を終えた。
創成川の変遷
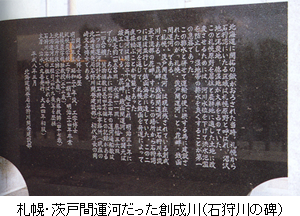
治水や排水をおもな目的に、明治28年から石狩の花畔から銭函をつなぐ「花畔・銭函間運河(樽川運河、山口運河とも呼ばれる)」が開削され、創成川は「札幌・茨戸間運河」として整備された。運河の設計は、「石狩川治水の祖」と呼ばれる岡﨑文吉だった。新川から取水して、花畔・銭函間運河に通水し、途中、水のエレベーターといわれる閘門(こうもん)も数箇所設けられ明治30年に竣工した。茨戸側から2番目の閘門付近には「太平神社」が設立され、相撲や芝居が行われる社交場だったという。札幌・茨戸間運河は昭和期まで利用され、その後は現在の創成川になった。
*新札幌市史、札幌市北区役所・エピソード北区