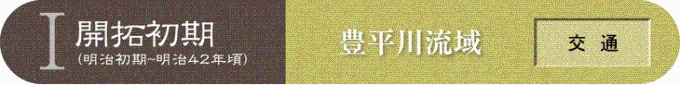開拓初期:豊平川流域-交通2【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
開拓初期(明治初期~明治42年頃) 豊平川流域 交通
硬石と軟石を運んだ軌道
明治5年、八垂別(はったりべつ)で硬石山が発見され、硬石の採掘がはじまった。また軟石も8年に穴の沢の石切山(石山地区)で採掘がはじまり、採掘量は年々増えていった。石材の運搬に道路が明治9年に整備された(石山新道)。新道には2本のレールが敷かれ、馬車鉄道として再整備された。石山から豊平川に架けられたトロッコ橋を渡り、八垂別の硬石を経由して、西11丁目を北進し南3条に至るルートだった。石だけでなく人も乗せるようになり、11丁目は「石山通」と呼ばれるようになった。
札幌軟石は、とくに明治25年の札幌大火で需要が増え、石造りの建物が札幌の街並みを飾った。また国際貿易港の小樽でも需要が高く、今も札幌や小樽に残されている。
明治37年には「札幌石材馬車鉄道」が創設され、現在の札幌駅まで延び、北5条西5丁目付近は石材の集積場所だったという。大正に入ると旅客輸送が中心になり、路線も増えた。そして大正7年の「開道50周年記念北海道博覧会」を機に電車に変わり、「札幌電気軌道」が開業し、昭和2年には市営になった。現在、市電は「西4丁目~すすきの間」だけが運行されているが、冬のササラ電車など札幌の風物詩でもある(北海道遺産)。
*参考資料/新札幌市史、札幌南区開拓夜話より
札幌軟石は、とくに明治25年の札幌大火で需要が増え、石造りの建物が札幌の街並みを飾った。また国際貿易港の小樽でも需要が高く、今も札幌や小樽に残されている。
明治37年には「札幌石材馬車鉄道」が創設され、現在の札幌駅まで延び、北5条西5丁目付近は石材の集積場所だったという。大正に入ると旅客輸送が中心になり、路線も増えた。そして大正7年の「開道50周年記念北海道博覧会」を機に電車に変わり、「札幌電気軌道」が開業し、昭和2年には市営になった。現在、市電は「西4丁目~すすきの間」だけが運行されているが、冬のササラ電車など札幌の風物詩でもある(北海道遺産)。
*参考資料/新札幌市史、札幌南区開拓夜話より
-
 明治42年に新築された石造りの拓殖銀行
明治42年に新築された石造りの拓殖銀行(北海道大学附属図書館蔵)
-
 現在の札幌市交通局の市電
現在の札幌市交通局の市電