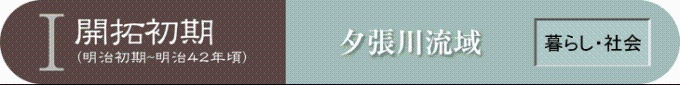開拓初期:夕張川流域-暮らし・社会【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
開拓初期(明治初期~明治42年頃) 夕張川流域 暮らし・社会
〈開拓初期の開墾の状況〉
馬追原野にはじめて入った開拓者は、元松前藩士で開拓使役人の下国皎三(しもぐにこうぞう)で、明治19年に由仁に入植し、開拓とともに北海道農業の推進にも貢献した。また同年、勇払ほか五郡長や札幌区長を務めた元前橋藩士(現・群馬県)の古川浩平も由仁に入植し、退官後は初代郵便局長を務めるなどまちの発展に尽くした。明治25年、鉄道の開通とともに由仁が開基し、26年には長沼、栗山、夕張を含む四つの戸長役場が置かれた。
南幌は宮城県の仙台藩支藩・角田藩主の石川邦光が家臣など250人余りを引き連れ、明治26年に石川地区に入植した。石川は家臣の水野太平に南幌全域の土地の調査と区割測量を命じ、水野は測量機を使って正確な測量を成し遂げ、基盤目状のまちが築かれた。長沼は明治20年に吉川鉄之助が入植して開村し、栗山は明治21年に泉麟太郎(いずみりんたろう)が入植して歴史が幕を開けた。心強い指導者が流域を切り拓いた。
南幌は宮城県の仙台藩支藩・角田藩主の石川邦光が家臣など250人余りを引き連れ、明治26年に石川地区に入植した。石川は家臣の水野太平に南幌全域の土地の調査と区割測量を命じ、水野は測量機を使って正確な測量を成し遂げ、基盤目状のまちが築かれた。長沼は明治20年に吉川鉄之助が入植して開村し、栗山は明治21年に泉麟太郎(いずみりんたろう)が入植して歴史が幕を開けた。心強い指導者が流域を切り拓いた。
-
 明治30年頃の和敬八号市街
明治30年頃の和敬八号市街(南幌町)
三角測量と長官山

明治7年、助手だったマーレー・S・デイが測量長になり、勇払基点の実測に着手した。五つの地点に標が立てられ、そのなかの第四標は馬追山だった。馬追丘陵のなかで最高峰の馬追山(瀞台)からは、当時の開拓使札幌本庁屋上の八角座を望むことができ、精確な三角測量の基準になったという。こうして太平洋から日本海まで、三角線を接続することができた。デイは明治8年、初の近代測量による「北海道実測図」を発行したが、測量は翌年に中断され、以後、日本人技師に引き継がれた。
馬追丘陵のなかには長官山がある。明治24年、渡辺千秋北海道庁第三代長官がこの山に登り、石狩平野の開拓構想を練ったことから、長沼と由仁の住民は「長官山」と呼んだのだ。
*参考資料/新旭川市史、由仁町史