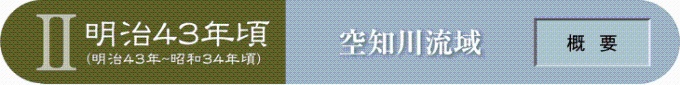明治43年頃:空知川流域-概要【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 空知川流域 概要
-
 大正の空知川流域図
大正の空知川流域図
空知川流域の開発 「激動の時代を乗り切る」

複数の産炭地を抱える空知川流域は、下富良野線(現・根室本線)が開通して一層の発展をみる。砂川に火力発電所、滝川には人造石油の工場が建設され、中空知の重化学工業地帯としての顔も持った。しかし人造石油工場は軍需用だったため、終戦後の経営はむずかしく廃止に至 った。滝川唯一の大工場の消滅は大きな痛手になったが、企業誘致を進め火力発電所の建設を成し遂げた。
またこの時代の大きな出来事に、大正15年の十勝岳大噴火がある。上富良野は再起不能とまでいわれるほどの被害を受けたが、長い年月をかけて復興に取り組んだ。いわば2度の開拓を経験し、美田を取り戻したのだ。