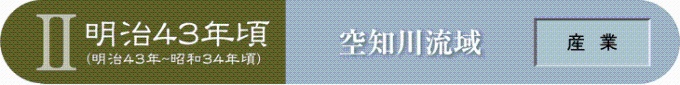明治43年頃:空知川流域-産業【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 空知川流域 産業
〈この時代の産業の状況〉

また明治31年に鉄道が旭川まで延びると、終点(空知太駅)として栄えた滝川から転出者が相次いだ。しかし大正2年の「下富良野線(現・根室本線)」の開通で、滝川はふたたび交通拠点の地位を取り戻し、「滝川商人」の商圏は上川地方全体に及んだという。「石狩火力砂川発電所(現・北海道電力砂川発電所)」が砂川に設置され、後に滝川にも誘致され、一帯は重化学工業都市の顔も持つようになる。また大正7年、芦別の野花南地区にわが国初のダム式発電所「野花南発電所」が竣功し、空知川水系の水力発電開発が行われ、まちに明りが灯った。
人造石油滝川工場

高度な技術水準の工場として昭和16年から操業されたが、戦後に人造石油の生産は中止された。大工場は「滝川化学工業」として新たに発足し、コークスやガスを生産したが、経営悪化のため昭和27年に操業停止に至った。滝川唯一の大企業の消失はあまりにも大きかったが、すぐさま大企業の誘致活動が行われ、全道一の規模を誇る北海道電力(通称・北電)滝川発電所が昭和35年から発電を開始した(現・北電テクニカルセンター)。
*参考資料/滝川市史