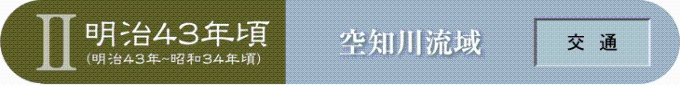明治43年頃:空知川流域-交通【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 空知川流域 交通
〈この時代の交通の状況〉
釧路を経由して根室に至る、「下富良野線(現・根室本線)」の「滝川~富良野間」が大正2年に開通した(10年に全線開通)。この開通は流域発展に大いに役立った。富良野は札幌との交通が便利になり、すでに開通していた「十勝線(現・富良野線)」と合わせ、道央圏の幹線鉄道が下富良野駅で交わり、交通の要衝とともに物資の集散地にもなった。また芦別では、下富良野線の開通で石炭運搬の炭鉱鉄道が敷設された。昭和10年には札幌と沼田をむすぶ「札沼線」が開通し、新十津川に「上徳富駅」と「北上徳富駅」が新設され、交通の便を高めた(昭和47年「新十津川~石狩沼田間」廃止)。
複線化やディーゼル機関車への転換など、鉄道の近代化が図られた点も大きい。
複線化やディーゼル機関車への転換など、鉄道の近代化が図られた点も大きい。
空知川が複線化を阻む

昭和33年8月の「北海道博覧会」から、待望のディーゼル機関車が「滝川~札幌間」を運行するようになり、さらにスピードアップした。一方、蒸気機関車は幹線から姿を消し、昭和50年には廃止された。
*参考資料/滝川市史
発電所の水で滝川駅構内を流雪
滝川は多雪地帯で、駅の除雪に毎年多額の費用が投入されていた。大雪が降ると、大量の貨車が構内にクギ付けになることもしばしばだった。そこで、駅構内に流雪溝をつくることになった。
昭和35年に「北海道電力滝川火力発電所」が完成し、大量の発電機冷却水が放出されることから、これを活用して大量の雪を融かすのだ。北電の協力を得て、昭和35年に完成した流雪溝は、軌道に沿って流雪溝が整備され、ラッセル車が通るだけで側溝に雪が集まり流されるしくみで、除雪がスピードアップされて大きな成果を上げた。その後、増設され、鉄道沿線やホームも排雪できるようになった。
*参考資料/滝川市史
昭和35年に「北海道電力滝川火力発電所」が完成し、大量の発電機冷却水が放出されることから、これを活用して大量の雪を融かすのだ。北電の協力を得て、昭和35年に完成した流雪溝は、軌道に沿って流雪溝が整備され、ラッセル車が通るだけで側溝に雪が集まり流されるしくみで、除雪がスピードアップされて大きな成果を上げた。その後、増設され、鉄道沿線やホームも排雪できるようになった。
*参考資料/滝川市史