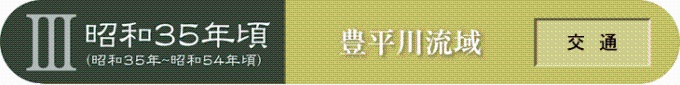昭和35年頃:豊平川流域-交通【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
昭和35年頃(昭和35年~昭和54年頃) 豊平川流域 交通
〈この時代の交通の状況〉
札幌がオリンピックを誘致した目的のひとつに、都市基盤整備のまちづくりがあった。寒冷積雪地の交通の切り札・地下鉄が開通し、昭和40年からは都心部への交通の流入を分散させるため、北一条通、厚別通、南郷通、羊ヶ丘通、創成川通と環状通などからなる「1バイパス1環状5大放射」が整備されていった。その頃の札幌は、約3世帯に一台が自動車を所有する(市統計書)、自動車社会をむかえていた。
鉄道は重要路線・千歳線の短絡線「新札幌駅」が開通し、また札幌に一番近い港・石狩湾新港の開発もはじまった。昭和35年に「東京~札幌間」にジェット機が就航し、飛行機での移動が2時間をきると、ふたつの都市間で人と物の交流が活発になった。
*参考資料/新札幌市史
鉄道は重要路線・千歳線の短絡線「新札幌駅」が開通し、また札幌に一番近い港・石狩湾新港の開発もはじまった。昭和35年に「東京~札幌間」にジェット機が就航し、飛行機での移動が2時間をきると、ふたつの都市間で人と物の交流が活発になった。
*参考資料/新札幌市史
千歳線と副都心の開発

(「国土画像情報(カラー空中写真)国土交通省」)
その頃国鉄は、「千歳線」の遠回り路線を解消する計画を立てていた。当初は、ひばりが丘団地を通過する予定だったが、札幌市と協議して厚別地区に駅を新設することに。住宅街の開発計画は、商業地中心の副都心に発展し、昭和48年に千歳線「新札幌駅」が開業し、52年にはショッピングセンターがオープンした。道内最大のプラネタリウムを誇る「札幌市青少年科学館」も56年に開館、翌57年には地下鉄東西線も延長された。交通網の発達とともに、新札幌副都心が誕生した。
*参考資料/新札幌市史など
地上も走る地下鉄

路線のなかで南北線の「平岸~真駒内間」は、地下鉄でありながら一部地上を走る。地下から一気に地上に上がる瞬間、緑に包まれた都市の姿が窓いっぱいに広がり、爽快そのものだ。地上部は旧定山渓鉄道の廃線跡が利用され、雪を防ぐためにアルミ合金製のシェルターで覆われた、世界で唯一の構造だ。