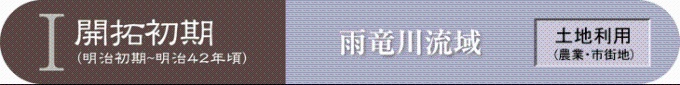開拓初期:雨竜川流域-土地利用2(農業・市街地)【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
開拓初期(明治初期~明治42年頃) 雨竜川流域 土地利用
雨竜を開拓した華族農場
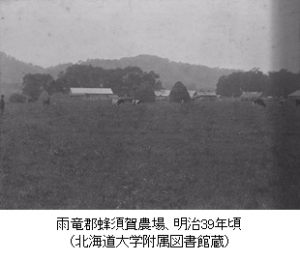
明治22年、三条実美(さんじょうさねとみ)と蜂須賀茂韶(はちすかもちあき)、菊亭脩季(きくていゆきすえ)達6人の華族は、資金を出し合って「華族組合雨竜農場」を設立し、翌23年に農場を開いた。西欧の大規模農場を目指し、初年度は月形の樺戸集治監の囚人が開墾にあたったが、その後は労働力が集まらず、24年には中心人物の三条が死去すると、明治26年に解散に至った。新たに蜂須賀はじめ3農場が開かれ、37年には蜂須賀農場かんがい溝が完成して、大正に入ると「米の雨竜」と称されるようになっていた。
明治26年に開設した菊亭農場は、屯田兵村の設置を見込み、明治27年に本通に沿って市街地を設定するなどまちの基礎も築いた。菊亭家が所有していた妹背牛の未墾地を森源三札幌農学校第二代学校長(現・北海道大学)が開墾して、妹背牛の歴史も明けた。
*参考資料/深川市の概要・開拓のころ、雨竜の歴史・農業編
沼田喜三郎と開墾会社
小樽で精米業を営み成功を収めた沼田喜三郎は、明治26年、沼田の未開地の貸下げを受け、「開墾委託株式会社(通称、雨竜本願寺農場)」を設立した。自ら社長に就き、明治27年に故郷の富山県砺波(となみ)から18戸を移住させた。翌28年から富山県と石川県の真宗本願寺の信徒から募集し、本格的な開墾を進めた。
同社は、収穫された農産物を一手に買って小樽市場で売り、開拓者の生活必需品も小樽港を経由して得ていた。会社の事業期間は10年を目途に、11年目に解散したが、道路をつくったり橋を架けたり、用水路をつくって造田を図るなど、まちの基礎をつくり農業生産環境の整備にも力を入れた。この村はそれまで上北竜村と称していたが、北竜村と間違えやすいため、大正11年、開祖にあやかって「沼田村」に改名された。
*参考資料/JA北いぶき・沼田町開拓の歩み
同社は、収穫された農産物を一手に買って小樽市場で売り、開拓者の生活必需品も小樽港を経由して得ていた。会社の事業期間は10年を目途に、11年目に解散したが、道路をつくったり橋を架けたり、用水路をつくって造田を図るなど、まちの基礎をつくり農業生産環境の整備にも力を入れた。この村はそれまで上北竜村と称していたが、北竜村と間違えやすいため、大正11年、開祖にあやかって「沼田村」に改名された。
*参考資料/JA北いぶき・沼田町開拓の歩み
旧屯田兵村を財源に水田化

その後、年々入植者が増え、開田を望む声が急増したため、秩父別の大部分と妹背牛の大鳳川以北、深川の一部をかんがい区域に、村営事業の一切をひき継ぐ形で、大正元年、「秩父別土功組合」が設立された。雨竜川から取水する、かんがい施設「朝日用水」が大正4年に完成した。
*参考資料/石狩川の礎、石狩川の水利