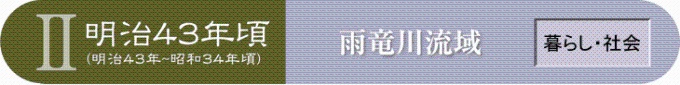明治43年頃:雨竜川流域-暮らし・社会【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 雨竜川流域 暮らし・社会
〈この時代のおもな出来事など〉
妹背牛は大正12年に深川から独立し、昭和27年に町制を施行した。大正12年には雨竜から北竜(現在の北竜、沼田、幌加内を含む)が独立を果たす。沼田は大正3年に、北竜から分離して「上北竜村」になる。大正7年には上北竜村から幌加内が分離し、大正11年に上北竜村は沼田に改称し昭和26年に町制が施行された。昭和34年には、秩父別が町制を施行して秩父別町になった。
流域の秘境・雨竜沼湿原

しかし平成2年に「暑寒別・天売・焼尻国定公園」の指定を受け、とくに雨竜沼湿原全域は「第一種特別保護地域」とされ、その自然の重要さが広く知られるようになると、行楽ブームも後押しして、現在は年間2万人もの登山者が訪れるようになった。このため地域住民を中心に「雨竜沼湿原を愛する会」が発足され、愛護活動が行われている。平成16年には北海道遺産に、17年には山地湿原としては世界初のラムサール条約に登録され、その知名度は世界的に高まりつつある。
*参考資料/伝説の湿原・雨竜沼(写真家・雨竜沼湿原を愛する会、岡本洋典)
音江ストーンサークル

これらの出土品は、本州に住んでいた者と交換して手に入れたと考えられ、墳墓(ふんぼ。墓)と結論づけられた。昭和3年に北海道指定文化財、昭和31年は国の史跡の指定を受けた。
*参考資料/新深川市史より