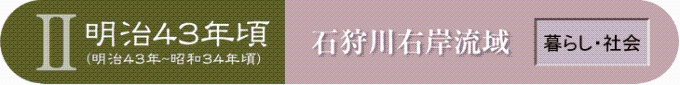明治43年頃:石狩川右岸流域-暮らし・社会【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 石狩川右岸流域 暮らし・社会
〈この時代のおもな出来事など〉
大正4年に新篠津が新篠津村になり、昭和22年に当別が、28年には月形が、そして昭和35年に浦臼が町制を施行した。
石狩川は広大な石狩平野を曲がりくねって流れ、洪水で流れを変え(自然短絡)、また捷水路事業で本川と切り離された、「河跡湖(旧川、三日月湖)」が中流から河口までに点在し、壮大な河川景観になっている。しかし住民にとっては、陸つづきだった地に本川が流れるようになったことで、暮らしに大きく影響した。
石狩川は広大な石狩平野を曲がりくねって流れ、洪水で流れを変え(自然短絡)、また捷水路事業で本川と切り離された、「河跡湖(旧川、三日月湖)」が中流から河口までに点在し、壮大な河川景観になっている。しかし住民にとっては、陸つづきだった地に本川が流れるようになったことで、暮らしに大きく影響した。
洪水が行政区を変えた

袋達布住民は行政的には北村に属したが、川を渡らねばならなかった。このため学校は新篠津の方に通うようになり、郵便物の集配も新篠津の郵便局が行うなど、日常生活は新篠津でまかなうようになった。このような事情から、大正9年、袋達布の住民から「新篠津の行政区域へ編入してほしい」という請願が出された。昭和5年になってようやく決着がつき、晴れて新篠津住民になった。
*参考資料/新篠津村百年史
次男・三男の開拓団
日本は古来から、長男が家業を継ぐことになっていた。しかし太平洋戦争で農業が一時期衰退すると、農業を継ぐことができない農家の次男・三男が農村にあふれるという事態が起こり、深刻化した。この対策として国は、次男三男を対象に、土木工事現場で働きながら技術者を養成する「産業開発青年隊」を創設したり、海外や北海道への移住政策を進めた。
新篠津には地元の次男三男と、道東や道外からの移住者を含めた開墾が、西篠津、西高倉、拓新などで昭和27年からはじまった。ちょうどこの頃、「篠津地区泥炭地開発事業」の篠津運河工事がはじまっていたため、開拓地は水田開発を目指した。北海道は、戦後の農村過剰人口の受け皿として、開拓された地もある。
*参考資料/新篠津村百年史
新篠津には地元の次男三男と、道東や道外からの移住者を含めた開墾が、西篠津、西高倉、拓新などで昭和27年からはじまった。ちょうどこの頃、「篠津地区泥炭地開発事業」の篠津運河工事がはじまっていたため、開拓地は水田開発を目指した。北海道は、戦後の農村過剰人口の受け皿として、開拓された地もある。
*参考資料/新篠津村百年史