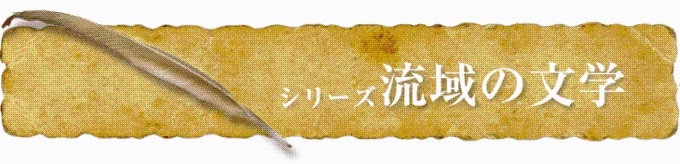明治43年頃:石狩川右岸流域-流域の文学【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
明治43年頃(明治43年~昭和34年頃) 石狩川右岸流域 流域の文学
本庄陸男「石狩川」
いの一番にこの川を見つけたのは、肥え太った鮭の群ででもあったろうか。

おこがましくも作者は「石狩川」の興亡史を書きたいと念願した。川鳴りの音と漫々たる洪水の光景は作者の抒情(じょじょう)をかき立てる。その川と人間の接触を作者は、作者の生まれた土地の歴史に見ようとした。そしてその土地の半世紀に埋もれたわれらの父祖の思いをのぞいてみようとした。
-
 「本庄陸男文学碑・石狩川」
「本庄陸男文学碑・石狩川」(石狩川の碑より)
また「石狩川」は、「大地の侍」として映画化され昭和31年に公開された。このフィルムは、現在は岩出山町と当別町が保有する2本のみの、幻のフィルムだ。近年、札幌のミニシアターで上映会が行われ、2回に分けて上映するほどの反響だった。12月には「函館港イルミナシオン映画祭」でも上映され、観客に大きな感動を与えた。時に彼等の前に立ちはだかり、大きな恵みを与えつづける母なる石狩川の川畔には、文学碑「石狩川」が建立されている。昭和39年7月の除幕式が行われてから今日まで、毎年「献花式」がつづけられ、本庄陸男の偉業を称えるとともに当別の財産として大切に守られている。
*参考資料/広報とうべつ、映画化された北海道の文学(北海道立図書館北方資料室所蔵資料展)、名作の中の北海道(木原直彦 著)
*参考資料/広報とうべつ、映画化された北海道の文学(北海道立図書館北方資料室所蔵資料展)、名作の中の北海道(木原直彦 著)
水に浮かぶと、川は限りもない広さであった。流れは一棹(さお)押して離れるごとにもりもりたくましくなった。…舟はつきとばされるのだ。そうして大きく迂回(うかい)する正面の淵にむかって、まっしぐらに押し流された。
本庄陸男
明治38年、当別町太美ビトエに生まれ、農業と雑貨商を営む家族と8歳まで過ごした。16歳で上京し、青山師範学校(現・東京学芸大学)を経て教員に就く。そのかたわら小説を書きはじめるとともに、プロレタリア活動に傾倒する。昭和5年に職を辞め、妻の病死や貧困生活に耐えつつ、昭和13年から文芸雑誌に「石狩川」を連載し、5回を連載後、後半を一気に書き下ろして小説「石狩川」を刊行。2カ月後の昭和14年7月23日、結核のため34歳の若さでこの世を去った。