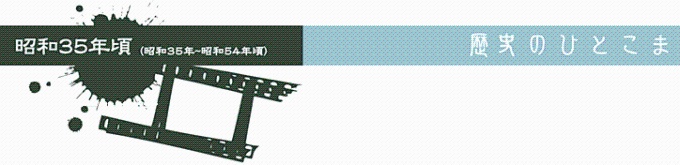昭和35年頃:幾春別川流域-歴史のひとこま【札幌開発建設部】治水100年
石狩川流域誌 支川編
昭和35年頃(昭和35年~昭和54年頃) 幾春別川流域 歴史のひとこま
郷土料理によるまちづくり
北海道は日本各地から開拓者が移住したことで、独自の食文化を育くんだ。
郷土料理は、ここでしか味わえないご当地グルメとして、今全国から熱い視線が注がれている—
郷土料理は、ここでしか味わえないご当地グルメとして、今全国から熱い視線が注がれている—
美唄の焼き鳥と焼きそば

ユニークな美唄焼き鳥を広めようと、平成18年に「びばい焼き鳥組合」が結成され、「室蘭やきとり」との食べ比べ大会や、全国の焼き鳥が味を競う「やきとりオリンピック」も開催された。美唄では、鳥のモツを米と炊き込む「鳥めし」も郷土料理だ。
またハンバーガーのように、歩きながら食べる袋入りの「味付ゆで焼きそば」は、炭鉱員が短時間で汚れた手でも食べられるよう考え出された。ソースの味が麺にしっかりしみ込み、炭鉱閉山後も子どものおやつとして定着した。昭和50年代後半、大手に押され生産は中止されたが、市民の要望で最近復活し、全国放送のテレビ番組に取り上げられるや全国区の人気になった。
参考資料/全国やきとり連絡協議会、美唄ファンポータブル
岩見沢キジ料理
わが国の国鳥・雉(キジ)は、北海道では昭和初期に狩猟や害獣の駆除などのために放鳥された。放たれたのは高麗雉(コウライキジ)で、岩見沢には野生化したキジがよく見られ、「雉ヶ森」や「雉橋」というキジに由来する地名などが残されている。
かつて上志文地区で雉生産組合が結成され、農家の副業などに高麗雉が飼われていたことがあった。平成10年になって社会福祉団体が取り組みを継承し、今では6,000羽を生産し、道内に限らず道外にまでキジ肉を販売している。また岩見沢の冬のお祭り「ドカ雪まつり」では、直径2mもの「ジャンボきじ鍋」がふるまわれ、郷土の味を広く伝えている。
参考資料/北海道・「産消協働」実践行動事例集
かつて上志文地区で雉生産組合が結成され、農家の副業などに高麗雉が飼われていたことがあった。平成10年になって社会福祉団体が取り組みを継承し、今では6,000羽を生産し、道内に限らず道外にまでキジ肉を販売している。また岩見沢の冬のお祭り「ドカ雪まつり」では、直径2mもの「ジャンボきじ鍋」がふるまわれ、郷土の味を広く伝えている。
参考資料/北海道・「産消協働」実践行動事例集
-
 高麗雉
高麗雉
-
 IWAMIZAWAドカ雪まつり
IWAMIZAWAドカ雪まつり(岩見沢市蔵)