25 雁来橋【札幌開発建設部】治水100年
ページ内目次
石狩川治水に係わる主な事業
25 雁来橋
戦争をはさんで下部と上部を施工
豊平川新水路は昭和7年から開削され16年に通水したが、札幌稚内線(現・国道275号)が新水路をまたぐ部分に橋が必要になった。通水前に橋の下部工事がはじまり、水が流れる部分は潜函(せんかん)を使って基礎工事が行われ13年に完成した。潜函とは、水が流れ込むのを圧縮空気で防ぎながら、なかで作業ができるようにしたコンクリート製・鋼製の箱のこと。工事はその後、戦争に突入したため上部は見送られ、木橋トラスが仮橋されて交通を確保したという。
終戦の混乱が収まった昭和32年から工事は再開されたが、下部は20年近く経過していたため、下部の橋脚の改造が行われた。そして構造はPC桁橋で中央部分はワーレントラス3連の溶接橋という、道内でもはじめての試みだった。最新の技術が結集された雁来橋は昭和34年に完成し、市内で最長の橋になった。その後、札幌発展とともに国道275号は台数と荷重ともに増加をつづけ、雁来バイパスが建設されることになり、約1㎞上流に雁来大橋が昭和55年に架けられた。3連トラスの名橋は解体された。
終戦の混乱が収まった昭和32年から工事は再開されたが、下部は20年近く経過していたため、下部の橋脚の改造が行われた。そして構造はPC桁橋で中央部分はワーレントラス3連の溶接橋という、道内でもはじめての試みだった。最新の技術が結集された雁来橋は昭和34年に完成し、市内で最長の橋になった。その後、札幌発展とともに国道275号は台数と荷重ともに増加をつづけ、雁来バイパスが建設されることになり、約1㎞上流に雁来大橋が昭和55年に架けられた。3連トラスの名橋は解体された。
-
 昭和52年頃の雁来橋
昭和52年頃の雁来橋(札幌市文化資料室所蔵)
明治43年頃
-
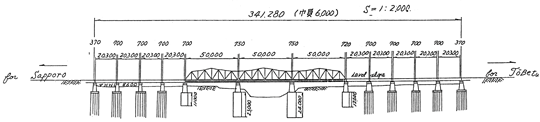 雁来橋の側面図
雁来橋の側面図
所在地
-
 札幌市東区東雁来
札幌市東区東雁来